安全性を確保するために整備したRQFDの枠組み
1914年の設立以来、コトブキはさまざまな施設になくてはならない椅子やサインといった設備を制作してきました。そして近年、最も出荷量が多いのが公園等に設置する遊具やベンチです。「公園の遊具は、子どもにとって楽しいものであることは重要ですが、当然安全性は最優先事項です」と品質保証部長の本間剛さん。
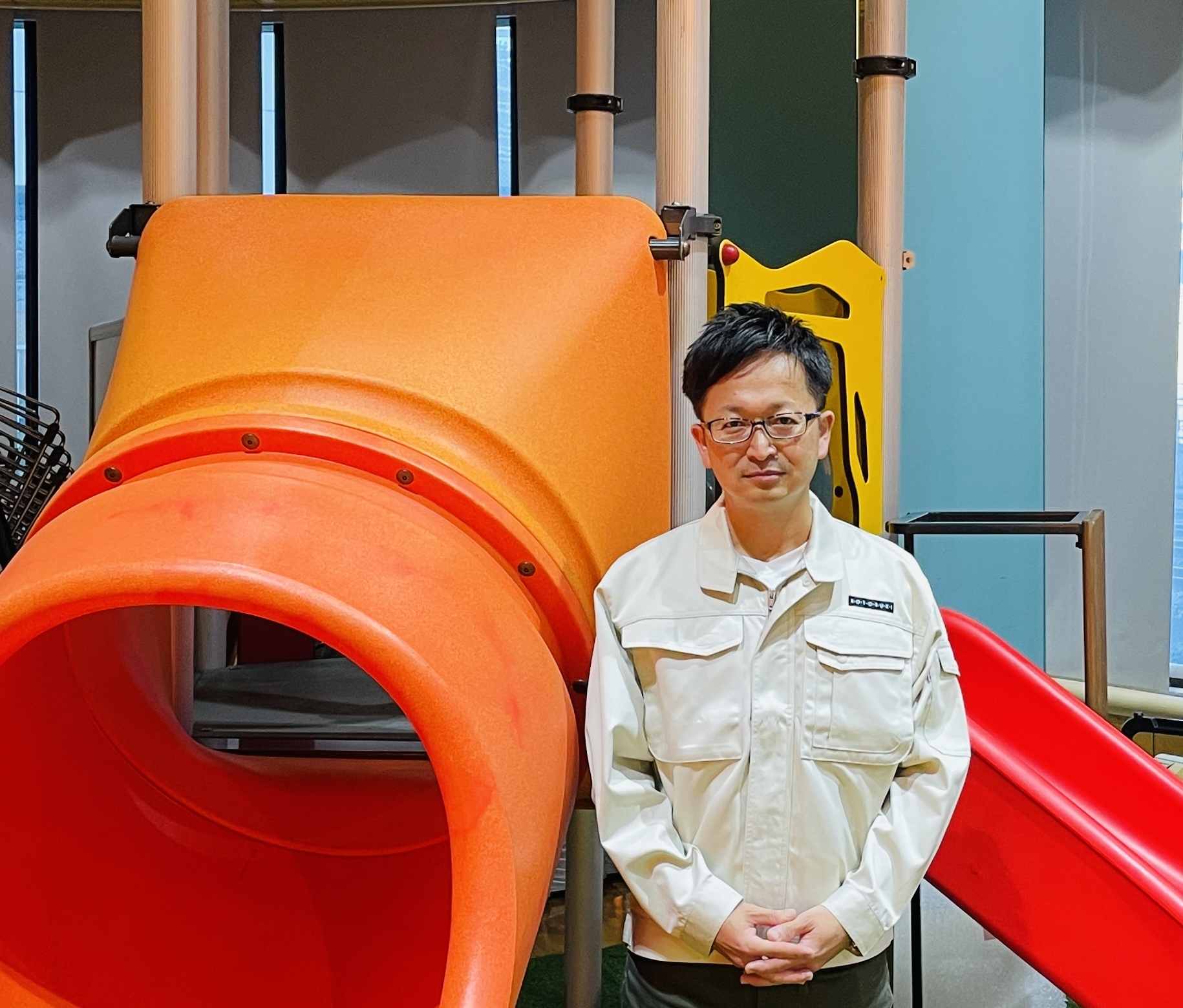
「遊具は10年、20年と長期で使われるものです。耐久性も高く、安全で安心できる製品を納めることが重要です。その中でも『強過ぎず、弱過ぎず』をポリシーに、コストと品質のバランスを見ながら最適な品質を探っています」(本間さん)
新製品の開発の際に特に意識しているのは、RQFDの枠組み。それぞれR=Requirement(必要条件)、Q=Quality(品質・特質)、F=Function(機能)、D=Design Basis(設計根拠)の略です。これにより取引先である地方公共団体の安全確保へのニーズに沿った高品質な製品づくりを意識するとともに、進捗状況をフェーズで区切り、都度承認を設けるなど、製品化する際のチェックの抜け漏れ防止に努めています。
塗装もスタンダードな溶剤塗装だけではなく、有害物質を含まない、人体や環境に優しい粉体塗装を使用し、厚みを持たせることで安全性と品質を担保するようにしています。
品質管理のポイントは「入庫」と「出荷」での丁寧な検品
コトブキの品質へのこだわりは、入荷から製造、そして出荷といった工場内の作業の中にも込められています。各工程ごとにその取り組みを見ていきましょう。「材料や部品を工場内へ入荷する際は、入荷検査課が社内の検査基準(JIS規程)に合わせて検査を行い入庫します。指示書に基づいて寸法や傷の有無を確認して、問題がなければ次の工程へ引き渡します」(本間さん)
コトブキではさらに、検品漏れの不良品が紛れ込まないように入庫処理された検査済みの製品にはバーコードラベルを貼るようにルール化されています。検品情報は自社で開発したフリーロケーション管理システムで管理されていて、検品情報がなければ次の工程へ進むことはできないとIT部の野村直祐さんは語ります。


こうした検査体制を運用するためには多くの時間を要しますが、品質の担保はそれだけの時間をかける必要があるものとコトブキの社内では理解されています。
「社内では定期的にパトロール活動やクレーム会議も行い、品質意識の向上を目指しています。また、業務の切り分けをしっかり行い、繁忙期は熟練した作業員が製造準備的なことをせず、組み立てに専念してもらえる環境づくりも進めました」(野村さん)

公園の遊具やベンチ、サインなどの状態を点検し、修繕する保全事業は、グループ会社である「コトブキタウンスケープサービス」が行っています。
「公園の遊具は思わぬ破損や腐食が進んでいる場合もあり、特に点検が重視されています。点検をして修繕が必要な場合は対処しています」(本間さん)
近年は各省庁でインフラ長寿命化基本計画を推進していることもあり、製品の修理・修繕サービス事業は加速しています。その一方で、過去の製品は古い図面を掘り起こす必要もあり、支柱など遊具の根幹となる部分に不具合があった場合、修理よりも入れ替えをする方が早くて安い場合もあるといいます。それまで蓄積してきた品質管理や製品の情報から、より効率の良い保全体制を敷くことがメンテナンスにおいて重要といえるでしょう。
全社での情報共有と状況確認で「次の事故」を未然に防ぐ
品質管理に積極的に取り組んでいるコトブキですが、事故が全く起きないとは考えていません。「事故が起きた際はスムーズに情報が共有される仕組みにしている」と本間さん。そのフローを確認しましょう。・事故の発生
→管理者や施主(自治体など)から営業担当に連絡が入る。
→営業担当が事故対応の専門アプリに事故内容を登録。
→アプリを通して経営幹部や関係者に一斉連絡が入る。
→品質保証部で初動対応。登録者(事故の報告者)の支援をしながら状況把握。
→各部門に情報が共有される。
(事故の状況や重篤度によって対応を切り分け、場合によっては対策チームを設営して集中的に対応)

事故には大小さまざまありますが、責任の所在が難しい事故であってもコトブキでは予見しておくべきことと捉え、ハザードとして対処する体制を整えています。
対処すべき事項としては遊具の修繕等はもちろん、事故当時の状況を確認し、遊具がまた同じ事故を起こさないように対策を講じることも含まれています。年々変化がある子どもの遊び方や体格・体力の変化なども含めて、あらゆる情報をもとに対策を検討し、製品設計に取り入れていきます。
「コトブキの特徴は、全国に支店・営業所があり、どこの都道府県でも 弊社の製品を使っていただいていることです。納品数や種類が多いということは、納品後に得られる情報量も増えることになるので、 営業担当が自治体様と連携し、さまざまな情報を伺い、その情報を社内に発信して共有し、事前に大事故にならないように取り組んでいます」(野村さん)
コトブキでは、こうした事故内容は事故対応の専門アプリに集約されており、関係者が確認することができるようになっています。
「事故があったとき、その事項を今後の製品開発に活かさなければなりませんが、遊具は遊ぶ以外にも成長を支える という側面もあります。安全に配慮し過ぎて、どんな年齢でも安全に、簡単に遊べて、簡単に達成できるものばかりを作るのは、遊具メーカーとして違うのではないかと考えています。安全面を徹底的に検討し、ハザードを無くしたうえで、子どもがチャレンジしたくなる面白い遊具を開発したい。そこを常に皆で一生懸命考えています」(野村さん)

子どもが使う遊具は安全・安心 であることが重要です。しかし、安全面だけを考えるのではなく、遊具で遊ぶ子どもの気持ちになって、挑戦したくなる遊具の開発にトライしています。子どもにとって何が大事なのかを多方面から考えて事業を推進しているコトブキの取り組みからは、安全と品質の向上を目指す真摯なモノづくりの姿勢が見えてきました。





