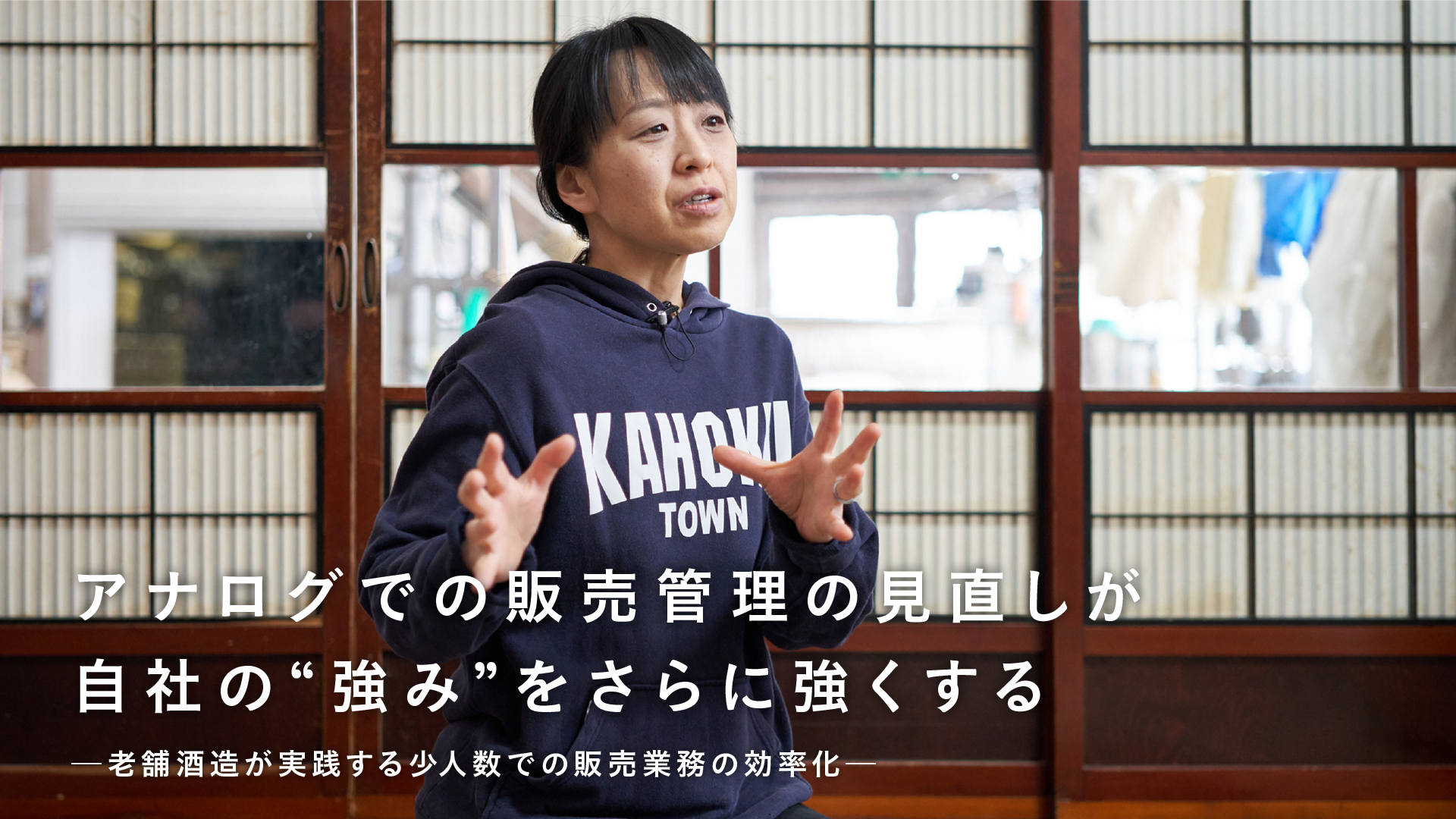1797年(寛政9年)に山形県河北町にて創業した造り酒屋。地元の酒米を原料に地域密着の酒造りを続け、「全国新酒鑑評会」「東北清酒鑑評会」といった日本の権威ある新酒鑑評会では最高賞受賞の栄誉にも輝いている。現在は9代目社長兼杜氏の和田茂樹さんと、バックオフィス業務等のサポートを中心に行う奥様の弥寿子さんが経営。主要銘柄に「あら玉」「月山丸」などがある。
https://aratama-wada.com/
少数精鋭でビジネスを行っている事業者にとって、さまざまな業務工程を効率化・最適化し、自社のストロングポイントに注力できる体制を構築することは喫緊の課題と言えます。その際に課題となるのは、「どのような手段・方法でその目的を達成するのか」です。今回は、家族を除いた従業員は季節労働の蔵人を入れて8名という少数ながらも、国内外のコンペティションで最高賞を何度も受賞するなど、多方面で高い評価を受けている山形県河北町の和田酒造の事例から、業務効率化・最適化のヒントを探っていきます。
ビジネスが上手く回っていても、常に課題意識を持って効率化・最適化につなげる

1797年の創業以来、山形県河北町で“地元に愛される酒蔵”を目指して酒造りを続けている和田酒造。日本酒の原料となる酒米の多くは栽培契約を結んでいる地元農家から調達され、出来上がった商品の約8割は地元で消費されているという“地元づくしのビジネスモデル”が確立されており、「常に業務の効率化や最適化に対する課題意識は持っている」と和田弥寿子さんは語ります。
「私たちが業務の効率化や最適化を行うのは、お客さまにより良い状態のお酒を飲んでもらいたいからなんです。業務が効率化・最適化されれば、よりフレッシュな状態でお酒を届けられるようになりますし、何より酒造りに力を入れられるようになります。だからこそ常に改善点を探していろいろと試しています」
本当に必要な作業とそれほど必要ではない作業、やるべきこととやらなくてもよいことをしっかりと仕分けすること。できるだけ必要ない工程を省いて必要なものに時間を回していくこと。それを徹底することで、お酒の品質がさらに上がっていく――。そのような考えで和田酒造は、効率化・最適化できる部分を見つけ、実際に改善してきたと言います。

「瓶詰め後になるべく短い期間でお客さまに商品を届けられるように、市場の動向を見極めて製造タイミングや貯蔵・在庫期間をコントロールする取り組みを実践するなど、品質保持・向上のためにさまざまな改善を行っています」(在庫管理について詳細の記事はこちら)
その中で最も効果が大きかったのは、一見酒造りと直接的な関係がないように思えるバックオフィス業務の改善でした。販売管理システムを機能的に活用し始めたことで、家族総出で取り掛かることになるほど大きな負荷となっていたバックオフィス業務の効率化や省人化が実現したほか、近年のEC需要の高まりやニーズの多様化に対してスムーズな対応ができたのです。
販売管理をデジタル管理に一本化し、精度の高い年間スケジュールを作成する

和田酒造では、どのようにしてバックオフィス業務の改善を進めていったのでしょうか。その取り組みを見てみましょう。
バックオフィス業務の改善の軸となったのは、販売管理システムの導入でした。
当時、経理業務を中心としたバックオフィス業務の課題として挙げられていたのが、
●アナログ作業(手計算)とデジタル作業(計算ソフトへの登録)の二重業務
●和田さんご夫妻とご両親が総出で対応を余儀なくされるほどの作業負荷の高さ
●拘束時間の増大による、酒造りをはじめとしたほか業務に割く時間の減少
といったもの。これらの課題を解決するために「経理に導入している販売管理システムを軸にしたバックオフィス業務の運用を始めた」と言う弥寿子さん。まず、アナログとデジタルを並走していた経理業務をデジタル作業に一本化すると、作業時間が激減。複数人で行っていた作業が一人でも対応できるようになり、作業負荷の高さに頭を悩ませることはなくなったと言います。
また、販売管理システムの導入は、作業負荷の軽減以外にもさまざまな成果につながりました。
●成果1:人為的ミスの激減
「計算や帳簿への記入をアナログ作業で行ってから、デジタルシステムに打ち直して管理する」という方法を止め、販売管理システムで作業を完結させたことで、アナログ作業時に散見していた人為的ミスが激減。さらに顧客情報や商品情報の管理がデジタル管理に一元化されたことで、受注時の手書きによる書き漏れ、転記ミス、お客様のファックスが判別できないということもなくなり、バックオフィス業務がスムーズに処理されるようになりました。
「以前は送り状も手書きで、都度大きな手間がかかっていました。しかし、販売管理システムなら一度お客さま情報を入力してしまうと、あとはボタン一つで完了してしまいます。二度目以降の登録は不要になるので、リピーターさん対応のことを踏まえると、かなり効率が的になったと思います」
●成果2:精度の高い年間スケジュールの作成
お酒は、原材料の酒米の収穫量や経済状況などの影響によって製造量や売上が増減することも少なくない“製造や販売の計画を立てることが難しい商材”ですが、和田酒造では販売管理システムに蓄積された、販売・顧客・在庫データを数値化して、需要予測、年間販売計画を立てていると言います。この年間スケジュールは、原材料の調達量や製造量も含まれた、かなり精度の高いものです。
「販売管理システムと在庫情報を紐付けたことによって、毎日の売り上げを打ち込むだけで在庫の状況や顧客別の商品の動きを把握できたり、前年のお酒の売れ行きやその時の気候、経済状況に合わせて“どういう商品が好評だったのか”ということが数値データで簡単にわかるようになりました。こういったことを把握してビジネスに反映させていくことは、アナログ管理ではとても難しいことでした」
●成果3:出荷・配送作業の増加へのスムーズな対応
新型コロナウイルス感染症の流行で加速化した「家飲み需要の増加(=商品発送の増加)」や、それに伴う「お酒の小容量化」への対応も、販売管理システムのおかげでスムーズだったと言います。
「製造に関しては、販売管理システムの売上データから酒問屋さんやお客さまのニーズを把握できていたので、製造量をコントロールすることで対応できています。また、受注数の増加や小容量化によって商品登録や出荷業務は増えましたが、各情報をデジタルで管理できていることや、作業が簡単でシステム化されているので負荷が高まった印象はありませんし、ミスもほとんど起きておらず、スムーズに対応できています」
販売管理システムを導入し、販売・顧客・在庫データを数値化して活用していくことで、戦略的かつ計画的にビジネスを展開していくことに成功した和田酒造。販売管理システムは、多くの企業が導入しやすいものであるため、そのノウハウは、みなさんも活用できるものでしょう。また、弥寿子さんは「特別なことはしていない」と語っていましたが、当たり前のことを当たり前にする(=改善できるところを改善する)ということも重要なのかもしれません。バックオフィスの改善は、業務プロセスの中でも比較的手をつけやすいもの。和田酒造の例を参考に業務効率化・最適化を目指してみましょう。