1937年に利器工匠具(ノコギリやカンナ、ペンチといった大工工具など)を販売する大都金物として創業。現在は、DIYカルチャー創造を推進する企業として、日本最大級のDIY工具通販サイト「ONLINE SHOP」やDIY専門の提案型通販サイト「DIY FACTORY」などを展開しています。山田岳人 Jackさんは、2011年に代表取締役に就任し、EC事業の成長に尽力してきました。
DIYカルチャー推進の企業理念のもと、ECサイトでの膨大な取り扱いアイテム数で支持を集める大都。少人数のスタッフで巨大な事業を運営するその背景には、スタッフの能力を最大限発揮するための“自由”な企業風土とオフィスの無駄を削減するコツがありました。代表取締役の山田岳人 Jackさんに、企業風土やバックオフィス業務への考え方を伺いました。
チームの生産性を高めるのは意見と実践の積み重ね
──大都では、社員は26名と少人数精鋭にされています。業務効率をあげて業務を拡大するにはどのような施策を打てばよいのでしょうか?
我々は少人数が良いと思っているわけではありません。ひとり当たりの生産性で考えています。 では、どうすれば生産性が高くなるのか? そのために大都では、「ポジティブに意見を言い合う」環境を大事にしています。

2012年にGoogleが「プロジェクトアリストテレス」という調査を行いました。これはどのようなチームが生産性が高いかを実験したものです。例えば1つのチームにずっと不平不満を言う人を加える。するとそのチームは全体に比べて生産性が2割落ちたそうです。逆にポジティブなチームは生産性が2割上がった。それは心理的安全性の違いだそうです。
我々のスタッフは一人ひとりの能力が高いわけではありません。MBAホルダーがいるわけでもないですし、超有名大学の出身者がいるわけでもない。ただ、チーム全体でみんなが自分の意見を出し合い、自分で判断して実践することを続けて来た。それが結果的に生産性の高い組織になっているのだと思います。こうしたチームをたくさん作って行くことが課題だと思っています。
先入観にとらわれず、無駄な作業や時間は削減していく
──今後、どの部署を強化しようとお考えですか?
カスタマーサポートのスタッフを増やして行くべきだと考えています。
EC事業を進めていく中で、業務の洗い出しをして、コア業務とノンコア業務に分けました。自社のサービスや強みに関わるシステム開発やデザイン業務のみがコア業務、それ以外の物流などはノンコア業務だと考えました。これは大都にとって、何が価値を生み出しているかを見つめ直した結果です。
その中でカスタマーサポートもノンコア業務と考えていました。それで、一度、派遣さんを集めてコールセンターを作ったことがあります。
でも、派遣さん全員に会社のビジョンを理解してもらい、その実現に向けて最大限のサービスをしてもらうことは実際難しいところがあります。あくまで問い合わせをさばいていくのが、彼らの仕事だからです。
お客さまとの大きな接点である業務は、企業イメージにも関わる重要なもの。よりお客さま対応を向上させるため、コールセンターはコア業務だったと改め、社内でやることにしました。もちろん、今後の事業の流れで今のコア業務がノンコア業務になりえることもあると思います。
──メーカーさんとの支払いのフローも改革されたそうですね。
通常なら、請求書はメーカーさんから送られてきます。例えば請求書に100万円とあれば、明細を見ずに払うのではなく、明細が合っているのかを確認するはずです。一般的にはそれを目で確認します。
当社ではいくらのものをいくつ仕入れたのかを専用のシステムで把握しているので、そのデータから支払い明細を作り、「今月はこれだけお支払いします」と渡しています。請求書は不要です。「支払い明細が間違っているのなら教えてください」と。このシステムはメーカーさんとAPI連携しているので、いつでもデータを確認することができます。そうした仕組み化を行うことで、お互いの手間も減り、ヒューマンエラーも防げるのです。
自社で開発した受発注システムを使ってもらうよう、メーカーさんにお願いしたとき、「使用料はいくらですか?」と聞かれました。受発注システムに利用料を請求するところもあるようですが、我々は無償で提供しています。我々が「使ってください」とお願いしているものに利用料を取ることはあり得ません。サポートも必要ですが、それも無償でバイヤー担当が行っています。
──仕組み化により、お客さまへのフローも変更したとうかがいました。
2年前に納品書を送付するのを辞めました。元々商品と一緒に同封する手間がかかっていましたし、違う納品書を送ってしまうミスもありました。こうした状況を受けて現場の方から「納品書をやめたい」と言ってきました。大丈夫かなと思ったのですが、実行してみるとクレームはありませんでしたね。
その代わりに、請求書や領収書が欲しいというお客さまはシステムから出力してもらえるようにしています。メーカーさんへの請求書の件もそうですが、システムを使ってきちんとデータを管理することで、思い切った効率化に踏み切れる面はあります。
このことで1年間でA4のコピー用紙を45万枚を削減することができました。環境にもよく、コストも下がりました。
また、資材を減らすために石油由来の包装を廃止し、紙の再生紙を緩衝材として使っています。梱包に使用するダンボールも、読み込むバーコード部分を刷り毛のデザインにしてわかりやすくし、バーコードを探す手間やタイムロスを省けるようにしました。
とにかく思いついたところから、さまざまな改善を取り入れています。

──テレワークの導入も早かったと聞きます。
2019年からテレワークを導入しています。コロナ禍に対応したとよく言われますが、実はたまたまなんです。
我々はリアルのコミュニケーションを大切にしていたので、リモートに対しては積極的ではありませんでした。しかし、男性社員2人が出産、子育てに立ち会いたいと言うので、試しにリモートにすることにしたんです。結果的にポジティブな影響が大きかったので、コロナ禍が始まった段階で、全員でリモートワークにすることにしました。
リモートワーク手当として月に3000円を支給しています。あと、仕事ができる環境にしてもらうためにスタッフにはデュアルモニターを、私が車でスタッフの自宅まで届けました。スタッフの家に行くのは初めてだったのですが、社員やそのご家族とコミュニケーションを取るいい機会になりました。テレワークというと管理側からするとネガティブな反応も多いですが、いざ導入してみると事業へのポジティブな影響も大きかったですね。
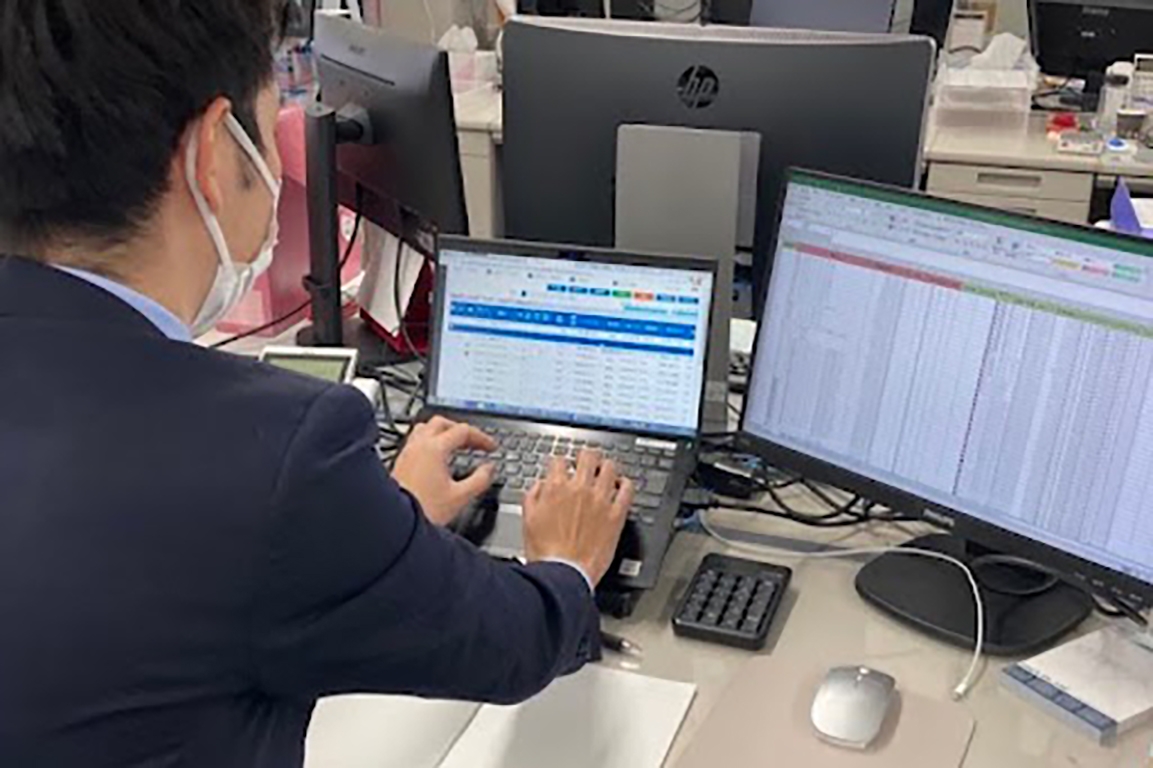
──あらためて、バックオフィスの効率化のうえでのポイントをお聞かせください。
当社の仕事の多くが、バックオフィスに関わるものです。自社のサービスに直結するからこそ、専用のシステムを中心に仕組みを整え、不要なものは削減してきました。請求書や納品書の廃止もその一環です。システムで管理することで、ヒューマンエラーをできる限り少なくなり、必要な情報にすぐにアクセスできるようになりました。
一方で、既存のやり方に慣れている人には導入の心理的ハードルが高い場合があります。ただ仕組みを押し付けるのではなく、丁寧な説明をしたうえで、誰もが喜ぶ形での効率化を進めることが必要でしょう。
また、大都では企業風土として、メンバー一人ひとりが自分の頭で考える、ということを求めています。
バックオフィスの業務改善は、トップダウンの取り組みばかりでは、なかなか進みません。普段の業務で気になったことを放置せず、その常識を疑い、日々小さな改善を積み重ねていかなければなりません。
また、そうした意見を気軽に言い出せる雰囲気も重要ですね。心理的安全性は世の中でもよく言われているワードですが、コミュニケーションを取りやすい環境が必要になります。私は山田岳人ですが、「Jack」とイングリッシュネームで呼んでもらっています。そもそも「社長」と呼んでいる時点で、社員の間にヒエラルキーがあるんです。これは日本ならではの企業文化だと思います。これでは自由に意見を言える企業風土は育ちません。そこで大都では、私含めスタッフ全員がイングリッシュネームで呼び合っています。

バックオフィス業務を充実させることで、スタッフのリソースや生産性は大幅に高まりました。この企業風土が大都の地力として、新しい挑戦を可能にしているんです。




